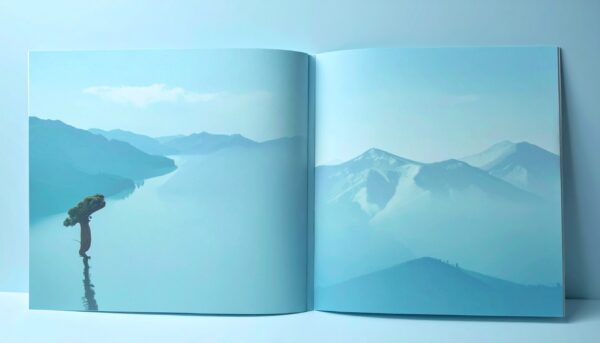印刷用語集

印刷注文の際によく耳にする印刷用語をまとめてみました。
| 名称 | 意味 | |
|---|---|---|
| あ行 | ||
| アウトライン | 簡単に言うとテキスト(フォント)をパス(図形)として処理すること。 | |
| 色校正(イロコウセイ) | 本番印刷前に行うテスト印刷した校正紙のこと。本機校正(実際印刷する機械で行う)、本紙校正(実際使用する紙で行う)、簡易校正(色校正機を使って行う)などいくつかの方法が存在する。 | |
| イラスト | 印刷に使う挿絵、絵のこと。イラストレーション。 | |
| イラストレーター | 職業のことじゃなくてAi(Adobe illustrator)のこと。イラレとも呼ぶ。Aiというファイルを使う場合はこのアプリが必須。 | |
| A判(エーバン) | 国際標準規格の用紙サイズのひとつ。同じ番号(例えばA4とB4のようなもの)で比較した場合、A判の方が必ず小さい。 | |
| 営業日発送 | 印刷通販で使う納期。例えば1営業日発送であれば、入稿と入金が完了した日(受付日)の翌日に発送を開始するという意味。発送してから配達までは納品地域により日数差が出るためこういう表記になっている。 | |
| 折(オリ) | 「おり」製本加工のひとつ。さまざまな折加工がある。折パンフレットと呼ばれる商品は折だけで冊子にしたもののことを指す。例えば3折なら6ページ、2折なら4ページになる。 | |
| 大判(オオバン) | サイズが大きいポスターに使う言葉。特別決まったサイズのことではない。感覚としてはA1やB1の規格サイズ以上になると大判と言い始める気がする。とにかく大きなサイズは大判。 | |
| オブジェクト | 印刷の紙面にある物体すべてを指す場合が多い。テキスト、イラスト、イメージなど。 | |
| オンデマンド印刷 | 簡単に言うとプリンターの業務用のようなもの。トナータイプのデジタル印刷機。 | |
| オフセット印刷 | 印刷会社と言えばこれみたいな現代の主流印刷方式。インクを使って印刷します。一般的に業界内では平版(ヘイハン)、枚葉(マイヨウ)と呼ばれます。 | |
| オフセット輪転 | 通称オフリン。巨大なトイレットペーパーのような用紙を巻き取って印刷するタイプ。チラシなどの超高速印刷はこれ。業界ではマキトリとも呼ぶ。 | |
| か行 | ||
| 画像 | 印刷に使う写真のこと。イメージ。 | |
| 規格サイズ | ISO規格の用紙サイズのこと。通常はA4とかB5とかのこと。A4と言われれば規格サイズ210mm*297mmのこと。対して規格ではないサイズは特寸(とくすん)と呼ばれる場合がある。 | |
| 化粧断裁(ケショウダンサイ) | 化粧断ち、化粧と呼ぶことがある。主にペラものを仕上げる断裁のこと。 | |
| 校正(コウセイ) | 印刷データの修正のこと。お客様と業者間のやりとりで行うもの。 | |
| 校閲(コウエツ) | 文章や表現内容の確認を行うこと。一般的に校正ではこの範囲のチェックを行なう慣習はないのでお客様側での注意が必要になる。 | |
| 校了(コウリョウ) | 校正が終了すること。発注主(お客様)が行うもの。 | |
| さ行 | ||
| CMYK(シーエムワイケー) | シアン(青・アイ)・マゼンタ(赤・アカ)・イエロー(黄・キ)・キープレート(黒・スミ)のこと。印刷ではこの4色を組み合わせてカラーを表現する。カラー印刷=4色印刷ということになる。RGBでデータを作ったとしても印刷現場ではそれをCMYKに変換して使う場合がほとんど。 | |
| 仕上がり(シアガリ) | ペラものなら断裁が終わった状態、冊子なら製本が終わった状態のこと。対して断裁や製本が終わっていないが印刷が終わった状態のものを刷本(すりほん)という。 | |
| 上製本(ジョウセイホン) | 糸かがりやアジロ綴じされた本文をボール紙のような厚紙を包んだ表紙で綴じる製本。耐久性が高いので長期保存するような冊子などはこの製本になることがある。他の製本に対してコストがかかる。 | |
| スクラム製本 | スクラム綴じ。綴じなしなどと呼ぶこともある。製本ではあるが綴じていないので分解できる。 | |
| 責了(セキリョウ) | 業者がお客様に替わってする校了を責了とよぶ。責任の所在などでしばしばトラブルを起こすこともあるので責了を禁止している会社も存在する。 | |
| た行 | ||
| チラシ | 最近はフライヤーとも呼ぶ。ビラ。配布方法などで呼び名が違うなど諸説ある。印刷業者としてはまず聞かないし使う機会はないけど、なぜか印刷通販の世界ではよく出てくるワード。チラシもフライヤーもどちらもチラシで間違いない。 | |
| DTP(ディーティーピー) | デスクトップパブリッシングの略。PCを使った印刷データを作る作業のことを言う。この作業を行う人間をDTPオペレーターと呼ぶ。 | |
| デザイン | 印刷物を「どのように」作るかを考案する作業。印刷物のデザインはグラフィックデザインと呼ばれる。 | |
| とんぼ | トリムマークのこと。断裁時や製本時に使うので必須とされている。一般的にトンボの間隔は3mm。 | |
| トリムマーク | とんぼのこと。断裁時や製本時に使うので必須とされている。一般的にトンボの間隔は3mm。 | |
| な行 | ||
| 入稿(ニュウコウ) | 印刷工程に原稿(データ)を入れること。 | |
| 中綴じ(ナカトジ) | 冊子の背側を針金で2箇所綴じる製本。似たようなもので平とじというものがあるがこれは別もの。 | |
| 塗り足し(ヌリタシ) | 印刷仕上げ時に断裁部分の白が出ることを避けるためのデータ処理。簡単に言うと仕上がりサイズの天地左右に3mmずつ絵柄を延長させてあげれば良い。 | |
| は行 | ||
| PDF(ピーディーエフ) | Adobe社のアプリケーション。これで作ったものがPDFファイル。 | |
| B判(ビーバン) | 国際標準規格の用紙サイズのひとつ。同じ番号(例えばB3とA3のようなもの)で比較した場合、B判の方が必ず大きい。 | |
| 左綴じ(ひだりとじ) | 冊子の表紙を正面にして左側が綴じてある冊子を左綴じ。一般的には横組(左から右に向かって文字が書いてある読み物)は左綴じにするのがセオリー。決まりはないけど横組を右綴じにした場合の違和感は大きい。 | |
| フォント | 文字の種類。機種に依存したものなので他で同じフォントを使っていなければ違うフォントに置き換わるという概念を持っておくことが重要。印刷の現場で最も多いデータエラーがフォント絡みのものである。 | |
| フォトショップ | フォトショとも呼ぶAdobe社のアプリケーションPhotoshop。PSDファイルを編集するなら必須アプリ。実は無くてもなんとかなるのがフォトショ。 | |
| ペラ | 1枚もののこと。冊子ではないのでページでは表現しないが、あえて言うとペラ1枚=2ページのこと。 | |
| ま行 | ||
| 無線綴じ(ムセントジ) | 冊子の背側を糊で綴じる製本。必ず表紙で包んで製本するので包み(くるみ)製本ということもある。並製本。 | |
| 見本(みほん) | サンプル・予備などとも呼ぶ。印刷成果品(完成品)はほぼロット生産のため通常予備が多く出る。その中からお客様に渡すものを見本と呼ぶことが多い。まれに極小ロットの納品数になると見本の方が多くなるというお客様には言い辛い状況も起きる。 | |
| 見開き(みひらき) | 冊子などの入稿時に使うデータの面付け方法。例えば4ページ左綴じの見開きデータであれば、1枚目が左から1・2ページ、2枚目が3・4ページというようにページ通りに開いた状態でデータを作る。一般のお客様にはこのデータ制作が1番ラクだと思うのでオススメ。 | |
| 右綴じ(みぎとじ) | 冊子の表紙を正面にして右側が綴じてある冊子を右綴じ。一般的には縦組(上から右に向かって文字が書いてある読み物)は右綴じにするのがセオリー。決まりはないけど縦組を左綴じにした場合の違和感は大きい。 | |
| や行 | ||
| ら行 | レイアウト | 印刷の体裁のこと。デザインされたものをレイアウトして印刷するという流れ。 |
| わ行 | ||
印刷用語は地域、会社単位でも使い方に違いがあります。私が経験してきた会社で使ってきた言葉を元に印刷通販などでよく見かける言葉の解説をしてみました。